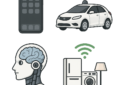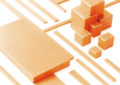C2680はJISに規定された黄銅(真鍮)の一種で、七三黄銅と呼ばれるC2600の銅を減らして亜鉛を増やした材料です。
C2600よりも強度や硬さが高いですが、展延性と加工性は少し劣ります。
C2680の特徴と性質
C2680は一般的に次のような特徴があります。
- 加工性が高い:冷間加工にも熱間加工にも対応可能。深絞りや曲げ加工に適しています。
- 展延性に優れる:他の黄銅材(C2600など)に比べても、成形性が良好です。
- 溶接性・ろう付け性:ろう付けやはんだ付けに適しており、接合性が高い。
- 電気伝導性・耐食性:電気特性や耐食性は純銅には劣りますが、日常使用には十分なレベル。

C2680の用途例
C2680はその加工性の高さから、さまざまな工業製品に使われています。
板材としての流通が多いです。
- 楽器部品(トランペットなどの管体)
- 水道・空調関連のパイプ
- 自動車用の金属部品
- 建築内装部品(ドア金物など)
- 家電製品の外装・装飾部品、端子・コネクター
C2680の化学成分(JIS H3100準拠)
C2680の主な化学成分は以下の通りです。銅:亜鉛=65:35の合金は黄銅2種とも呼ばれます。
| 元素 | 含有量(%) |
|---|---|
| 銅(Cu) | 64.0~68.0 |
| 亜鉛(Zn) | 残部(約32~36) |
| 鉄(Fe) | ≦0.05 |
| 鉛(Pb) | ≦0.05 |
| スズ(Sn) | ≦0.01 |
※上記はJIS H3100の冷間圧延材・熱間圧延材などに基づく値です。
C2680の質別ごとの機械的性質(JIS H3100準拠)
C2680には用途や加工性に応じてさまざまな質別が規定されています。加工硬化によってそれぞれの機械的性質になるよう調整されています。
以下に、代表的な質別の性質を一覧で示します。
| 質別記号 | 厚さの区分 | 引張強さ (N/mm2) | 伸び (%) | 特徴・用途例 |
|---|---|---|---|---|
| O | 0.1以上 0.3未満 | 275以上 | 35以上 | 加工用。柔軟性が高く深絞りに適する。 |
| 0.3以上 30以下 | 275以上 | 40以上 | ||
| 1/4H | 0.1以上 0.3未満 | 325~420 | 30以上 | 柔軟性が高く塑性加工も可能。(H:Hard) |
| 0.3以上 20以下 | 325~410 | 35以上 | ||
| 1/2H | 0.1以上 0.3未満 | 335~450 | 23以上 | 強度と加工性のバランスが良い。 |
| 0.3以上 20以下 | 335~440 | 28以上 | ||
| 3/4H | 0.1以上 0.3未満 | 375~490 | 10以上 | 強度が必要な部品などに使われる。 |
| 0.3以上 20以下 | 20以上 | |||
| H | 0.1以上 10以下 | 410~540 | – | 高強度。バネ性や剛性が必要な部品に用いられる。 |
| EH | 0.1以上 10以下 | 520~620 | – | 極めて高い硬さを持ち、耐摩耗性が求められる用途などに。(EH:ExtraHard) |
- 上記は板の特性です。厚さによって若干の差異があります。数値は代表値です。
- 棒材や線材では、引張強さは材径や加工条件によって変動しますが、一般に冷間加工によって高強度化できます。
- 特に線材はばね用や引張荷重を受ける構造に使われるため、HまたはEHの質別が多用されます。
C2680の物理的性質(物性値)
C2680は以下のような物理特性を持ちます。類似材質の値なので参考に留めてください。
| 項目 | 数値 | 単位 |
|---|---|---|
| 密度 | 約8.47 | g/cm3 |
| 比重 | 約8.47 | - |
| 熱伝導率 | 約120 | W/(m・K) |
| 電気伝導率(20℃) | 約28 | %IACS |
| 線膨張係数(20~300℃) | 約20.9 ×10⁻⁶ | /K |
| ヤング率 | 約100 | GPa |
| ポアソン比 | 約0.34 | – |
C2680と環境負荷物質・規制対応
◆ C2680に含まれる有害物質(JISに準拠)
| 元素 | 含有量上限 | 備考 |
|---|---|---|
| 鉛(Pb) | ≦0.05% | RoHS指令の対象物質(許容上限:0.1%) |
| カドミウム(Cd) | 基本的に含まれない | 旧型の黄銅では添加例もあったが、C2680では使用されない |
| 水銀(Hg) | 含まれない | – |
| 六価クロム(Cr⁶⁺) | 含まれない | – |
| PBB/PBDE | 含まれない | 難燃剤として使われないため対象外 |
C2680はJIS規格で鉛などの有害元素の含有量が制限されており、RoHS2指令(EU)、ELV指令(自動車向け)に適合しやすい材質です。
ただし、再生黄銅材を用いる場合は、カドミウムがRoHS指令の閾値:0.01wt%(100ppm)を超える可能性があるため注意が必要です。
RoHSに適合させる場合はカドミレス材を指定する必要があります。
機械設計者がC2680を使う際の注意点とトラブル事例
C2680は加工性・経済性に優れた材料ですが、設計・使用条件によってはトラブルの原因になることがあります。
以下に注意点と実際に報告される問題例を整理します。
◆ 設計上の注意点
| 項目 | 内容 | 解説・対策 |
|---|---|---|
| 応力腐食割れ(SCC) | C2680はアンモニア性環境や湿潤雰囲気下でSCCを起こしやすい | 高湿・薬品環境で使用する際は、コーティング・材質変更(脱亜鉛合金など)を検討 |
| 脱亜鉛腐食(dezincification) | 長期間水に接触する環境で亜鉛が選択的に溶出し、脆くなることがある | 特に給水系配管では、脱亜鉛防止処理済みのC2700系やC3771などの使用を検討 |
| 疲労耐性が低め | 動的荷重の繰り返しを受ける用途では疲労破壊の懸念がある | 応力集中の少ない設計、厚みの増加、他材質(ばね鋼など)への変更検討 |
| 導電性の過信 | 銅に比べて電気伝導率が1/3程度であり、電流容量や発熱量に注意が必要 | 導電部品に使う場合は断面積や放熱性を見込んだ設計を行う |
| はんだ付け時の熱影響 | はんだ処理中の過熱で変色や寸法変化、脆性破壊を起こす可能性 | 局所加熱、フラックス選定、急冷回避などによるプロセス管理を |
◆ 実際のトラブル事例と対策
| 事例 | 発生状況 | 原因 | 対策 |
|---|---|---|---|
| 住宅設備の水栓バルブから水漏れ | 長年使用後に微細なクラック | アンモニア性腐食によるSCC | 鉛低減、亜鉛低減、スズ添加 |
| プリント基板のコネクタ端子が破断 | 圧入後の経時破壊 | 応力集中+環境中の腐食成分 | 曲げ加工形状の見直し+表面防錆処理 |
| 装飾品(楽器パーツ)が黒ずむ | 保管中の変色 | 空気中の硫黄成分による硫化 | 防湿・防錆処理、またはクロムメッキで表面保護 |
| ばね板が折損 | リレー接点の弾性部 | 荷重集中+材質硬度不足 | H質や他合金(リン青銅など)への変更を検討 |
まとめ
C2680は、バランスの取れた機械的性質と加工性を持つ汎用性の高い黄銅材料です。
特に深絞り加工や装飾用途など、形状や美観が重視される製品に適しており、銅合金の中でも使用頻度が非常に高い材料のひとつです。